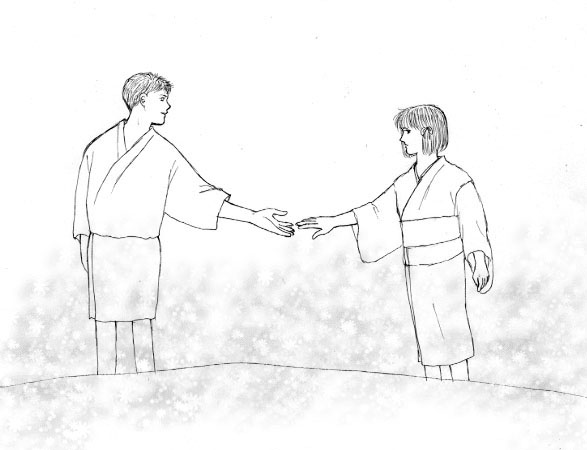
世界が終わるまで
えにし
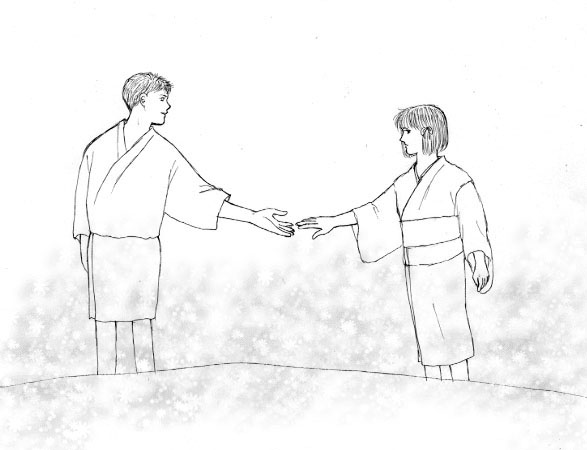
バスケットという、日本のプロ世界ではまだメジャーとは呼べなかったスポーツを、世間に浸透させたともいえる年代だった。芸能人のようにその名が知れ渡ることを、流川楓も桜木花道も望んだわけではない。けれど、本人たちの思惑とは別のところで勝手に一人歩きするものだ。そして、自分たちにプライベートがなくなるとは思ってもみなかったのである。
「ちっ」
「撒いたか?」
「…さー」
どこへ行っても目に付く長身は、たとえ一度撒いたとしてもまた次が現れる。まるでゲームのようだと花道はときどき思う。サングラスや帽子などの変装も、たいして役には立っていない。流川に言わせれば、
「テメーみてーな髪はいない」
だから、どうしてもばれてしまうのだ。こう言われると花道は言い返すこともできないが、実は二人揃って歩いているために余計目立っていることには、二人とも気付いていなかった。全日本メンバーの二人は、日常がバスケットで成り立っている。オフシーズンの企業同士の試合などでも、同じチームメンバーとして活躍していた。
「腐れ縁…」
すっかり大人になった今でも、流川は花道に毒舌しか吐かない。そして、それに対して花道が大声で応援するのも10年前から変わらない。一時期、大学やアメリカなど進路が違っていたのに、いつの間にかそばにいる。その上、いつの間にかバスケット以外でも近づいていた二人だった。滅多にない休日を楽しもうと、花道は流川を小旅行に誘った。関東圏内ではもうデートすら出来ない。少しでも離れればマシ、という花道の考えは、やはり甘かった。
「…京都だって人が多い」
流川の感想はもっともだった。ただし、これは実際に来てみてから思ったことで、旅行の話はちょっと嬉しかった。こんな関係になってから、夜以外に二人きりになることもできなかったから。
「…シーズンじゃねぇと思ったのによー」
二人でいても会話は弾まない。けれど、二人でゆっくり歩いたり、落ち着きたかった。今回のことで自分たちにはそれも困難だと、本当に身をもって知った。流川が『嫉妬』という言葉を覚えたのは、花道との関係が始まってからだった。バスケットの技術に関しては人を羨ましいと思ったことはあるが、それは目標であり努力への促進力となるもので、妬みではない。けれど、流川は自分ではどうにもならないイライラを持て余すようになっていた。それは、花道がファンというおっかけを邪険にしないからだ。
「テメーが甘いから、つけ上がる」
「…何のことだ?」
フェミニストな花道の行動が、流川には理解できない。文句用語は離れていた間にグレードアップされている。流川は相変わらず容赦なかった。
「鼻の下伸ばしやがって」
「だっ だれがだっ!」
「…グルーピーを拒めねーくせに」
「ち、ちがう! 俺はそんな」
「尻軽」
さすがの花道も頭に血が上る。ちっとも思いやりのないこの相手と、自分はどうして一緒にいたいと思うのだろうか。冷たい目線に怯むことはないけれど、胸に氷が飛んでくる気もする。
「こ…このバカギツネ…言わせておけば…」
低くなった声に、流川は顔を逸らす。このようなケンカは日常だけれど、今回の最後の言葉はさすがに花道の堪忍袋の緒が切れた。言葉だけでは足らず、久しぶりに手足を伴ったケンカをしようとした矢先、流川はスタスタと歩き出した。
「おいコラ、ルカワ!」
「…うるせー…どあほう」
流川は、嫉妬する自分もそれを丸出しにする自分も、情けないと思っていた。理性で動くはずなのに、感情のまま止まらなくなる。そんな自分に、まだ慣れていないのだ。
対して、花道もまだどこか落ち着かない気持ちに振り回される。シアワセだとうっとりしたり、立ち往生してしまうような関係に、つい突っ張ったりしてしまう。
こんなとき、高校生の頃のように何の気兼ねもなくケンカできれば、とどちらも思う。今は、互いの身体を大事にすることを多少は知った二人だった。だから、言葉が必要なのに、どちらも口が不器用なままだ。なかなかうまくいかない。
「この、バカ野郎! 迷子になっても知らねーぞっ!」
角を曲がって消えた背中に、花道は少し心配そうに毒づいた。自分ですら自分の位置がわからないのに、と思う。けれど、すぐに首を振る。
「し、知らん…知らねーぞ。あんなヤツ…」
どうしてああも可愛くないのだろう。花道には流川の嫉妬は、ただバカにされているようにしか見えない。女の子たちに焼き餅をやいていると想像すらできなかったのだ。説明してくれないから、いつまでもわからない。
それなのに、どうして自分はこんなにも好きだと思うのか。ずっと言い続けてきた「キライ」は、照れ隠しでもある。最初にそう口にしてしまったから、それしか言えなかった。
「あーもー、止め止め。あんなヤツのこと考えねーことにする」
ふんと鼻息を荒くして、花道は流川と逆方向に歩き出した。大股で、ついてくる相手もペースも気にせずに、ズカズカと音を鳴らすように歩く。何も考えないようにしようと決めても、頭にはあの冷たい表情しか浮かばない。想像の中の流川は、帰り道もわからないままその辺で寝始めた。それが、現実に近いことを花道は知っている。
「る…ルカワ…」
花道は、バスケットの試合中のように瞬発力とスピードを駆使して、流川を追いかけた。一方、ムカムカを押さえられないまま何も見ずに歩いていた流川は、行き止まりの壁の前でさすがに止まった。そのおかげで、少し冷静になれた。
「…だせー…」
これまでの行動を思い出して、流川はバツが悪かった。何度か深呼吸をして、空を見上げて肩を落とす。落ち着くと、一層情けなく感じた。
高校を卒業してから再会するまでの間、流川は何度も花道を思い出した。なぜ自分の記憶から消えないのか不思議だったし、誰かと少しでも近しい関係になりかけると必ず顔が出てくる。そんな存在だった。いつだったか、それが恋だと知ったけれど、流川が取るべき行動の回答はなかった。
花道との出会いが強烈だからか、流川は15歳以前のことを思い出したりしない。そんな自分に苛立ったりする。素直に照れることができなかった。
元来た道をゆっくりと戻りながら、流川は自分たちのことを考えていた。そして、悔しいけれど、このような知らない場所では花道がいないと戻れないことにも気が付いた。この京都旅行の段取りは、すべて花道が手配した。自分が泊まる旅館もわからない。荷物は駅のロッカーだったから。
「…ちくしょう…」
流川は嫉妬した自分にも、無駄な行動をした自分にも毒づいた。
早足がだんだん小走りになり、ついには必死で花道を探しに戻った。
行きと帰りでは風景が違って見える。戻っているつもりの流川は、自分がまた初めての場所に来ていることにすぐ気が付いた。けれど、さっぱりわからなくなり、動くことを躊躇した。
「…前にも…あった?」
どこかで迷子になった記憶があった。父親や母親に探されるものでもなく、それがいつだったかも場所もわからない。けれど、流川はデジャブを感じていた。
「道が細くて…人に会わなくて…」
言葉にすることで、小さな不安を一緒にはき出した。
ふと耳を澄ますと、遠くで人を呼ぶ声が聞こえた。
「…あの、どあほう…」
大声で自分を呼ぶ声にホッとした自分がまた悔しい。駆け引きめいた恋に、流川は負ける気はなかった。けれど、このときは素直にその方向に向かった。
その道に入った瞬間、また何かの情景が瞼に浮かんだ。心臓が音を立てるように鳴り響き、何かを感じて肌で緊張する自分を流川はコントロールできなかった。
「…あれ…」
うっそうと茂る森のような神社に、流川は間違いなく見覚えがあった。そして、花道の声は、そのずっと奥から聞こえるのだ。
やはり自分はここに来たことがある、そう感じながらも、確信のもてないことにはあまり興味がなかった。けれど、冷や汗が伝う前進は正直だった。
少しずつ花道の声が大きくなって、自分一人ではないのならと前へ進む。声だけでなく、あの暑苦しい顔が見たい。心からそう思った。
「…桜木…?」
軒下を曲がったところに、また別の小さな建物があった。そしてそこには、高齢の女性が静かに座っていた。
驚いて立ち止まった流川に、その女性はしわくちゃな笑顔を向けた。
「おや…ぼうやは…えーっと…」
人なつっこい仕草に、流川は少し緊張を解いた。けれど、その言葉はいただけなかった。
「…ぼうやじゃねー」
「ほぅ…そうだね、こんなに大きくなってまぁ…」
そう言いながら、立ち上がっても小さい姿を、流川の隣に並べた。
「……ばーさん…誰?」
「おや…」
「ここに、俺くれーのヤツ、来なかった?」
性急な会話の進め方に、その女性は返事をしないで座るように促しただけだった。
「何が聞こえてここに来た?」
「…はっ?」
突然の質問に驚いた。そして、また鳥肌が立つ自分が不思議だった。
「…さっきの桜木とかいうのに呼ばれたのかぃ?」
「……ばーさん…」
流川はこの女性に会ったことがあることをほぼ確認した。だから、花道のことを聞かれても驚かなかった。
「………思い出した。妖怪ババア」
「アハハハハハハ……相変わらず失礼なぼうやだねぇ…」
婆と呼ばれた女性は、それでも明るく笑った。
「…でも、それだけだ。今まで忘れてた…」
「そりゃあまあ…妖怪だからねぇ…」
「…ほんとに妖怪だったのか?」
「…お前さんがそう行ったんだよ」
そして二人で小さく笑った。
ずっと忘れていたけれど、確かに暗い森のような神社で、このお婆とこうして座って話したことがある。けれど、流川は途切れ途切れしか思い出せないでいた。そして、自分が「ぼうや」と呼ばれた頃から約14年経っているのに、お婆の姿形が全く変わっていないというところまでは、考えが及ばなかった。
「…ばーさん…俺、桜木に呼ばれてここに来た…」
「そうかぃ」
「…それって何だ? 前は何だった?」
このお婆の前では、今より少しは話す少年に戻ったようだった。
お婆はその問いには答えずに、またはぐらかすように別のことを聞いた。
「桜木…下の名前は何と言うんだぃ」
「…花道」
「ずいぶん目出度い名前だねぇ」
「………」
頭も目出度いと思ったことを、流川は口にはしなかった。
「お前さんの名も雅だし…そうか…ちょうど千年…くらいだからかねぇ」
「…ばーさん?」
「別に思い出さなくてもいいんじゃないかね…ちゃんと出会ったようだし」
「……わかるように話せ」
お婆は少し間をおいてから、低い声で話し始めた。
「この世の人はすべて『縁』で結ばれておる」
「…えにし?」
「聞きたいかや?」
「…さあ?」
「……全然変わってないねぇ、お前さん」
体を揺らしながら小さく笑うお婆に、流川はそれでも辛抱強く待った。何か、そうしなければならないような、無言の圧力を感じていた。そしてそれは、決して不快だと思わないから、流川自信本当に不思議だった。
「…忘れて当然のことだし、わざわざ思い出しても結局忘れるんだろうけど…」
「はっ? 聞こえねー」
「うーん…どうやら、仲違い中のようだし…」
そんなことまでわかるのは、妖怪以上ではないだろうか。流川は真剣に思った。
「ま…まあ見ておいて…」
「…見る?」
「以前のお前さんには体験してもらったけどね…その記憶を見ておいで…」
「…なんだそりゃ…」
お婆は流川に顔を近づけて、急にひそひそ声になった。
「…お前さんの、縁で結ばれた相手だよ…誰だかわかるかな…」
まっすぐにお婆の目を見返した流川は、軽いめまいを感じた。体がぐらついて、やばいと思った瞬間に、深い眠りに引き込まれていった。正確には、意識下だけ目覚めさせられたのだ。流川は、自分の記憶を辿り始めたのである。
2003.2.23発行
2012.4.6UP
next