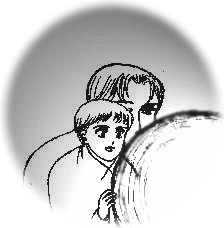オスカーとフェリックス
=昼間のパパはちょっと違う=
フェザーン全土の子どもたちの、トライヤルウィークが来た。早い話が各施設見学ツアーなのだが、授業参観とは逆であり、親たちは自分の子どもたちが自分たちの職場に来ることを、それほど喜んではいなかった。新しい帝国となってから、今後の人材育成のためにはじめられたこととはいえ、ほとんどが困っていた。
帝国軍大本営の幕僚たちも、ほぼ同じような思いでいた。そう感じないのは、自身の子が小さく託児所に預けられていないので参加予定のない、そして子ども好きなミッターマイヤー元帥くらいであった。
「仕事というものがどういうもので、親たちが昼間どんなことをしているのか、知っておくのは大事なことではないか」
蜂蜜色の髪を振り乱し、僚友たちに熱弁する。
一同も理解はしているし、強く反対はしなかった。実のところ、ただ、照れくさいだけなのだ。そしてそう口にするのがもっと照れくさいので、誰も言葉を発しなかった。そして今回、最も注目されているのはロイエンタール父子であった。彼が、どんな父親ぶりなのか、親友以外知らないのである。とてもじゃないが、以前のロイエンタールからは、「父親なロイエンタール」が、誰にも想像出来なかった。もちろん、これも誰も口にはしないが、皆が同じ思いでいた。
当日、シスターたちに連れられた子どもたちが、物珍しげにウロチョロし始めた頃、たまたま受け付け付近まで降りてきていたミッターマイヤーが、フェリックスを見つけた。
「フェリックス!」
そう呼びかけると、にこやかに振り返り、ファーターの元へ走り寄る。スカイブルーの瞳を見つめながら、ミッターマイヤーは小さな体を抱き上げた。おのおのが、シスターか保護者の元にいれば良いことになっており、フェリックスはファーターと共に1日をスタートした。
「ファーター、オスカーは?」
「さて。執務室かな。行ってみるか?」
「ファーターのお部屋に行ってからがいい」
フェリックスは、ファーターもオスカーも気になるらしい。小さいなりに気を使っているのかと感じたミッターマイヤーは、フェリックスの希望のままに行動した。
ファーターの執務室では、たくさんの部下たちがいて、その中でも背の高い深いブルーの瞳のお兄さんは、自分を見て意外そうな顔をするのを、フェリックスも目を丸くして見つめ返していた。
「なんだ? バイエルライン」
ミッターマイヤーも黙ったまま固まった部下を見て、思わず聞いていた。
「あ、いえ。失礼いたしました。何でもありません」
ロイエンタール閣下より、ミッターマイヤー閣下の方がお父さんっぽいなんて口にしたら、実直な上官が親友をかばい、怒られそうだと思いました、なんて思いは、心の中だけに閉まっておいた。
ファーターの昼間の居場所を一通り見て満足したらしいフェリックスを連れて、ミッターマイヤーはロイエンタールの執務室を訪ねた。部下の一人に、ベルゲングリューンと打ち合わせ中だと聞き、彼が退出してくるまで待つことにした。しかし、多忙なミッターマイヤーは、5分もしないうちに部下に呼ばれ、行ってしまった。もちろんフェリックスを置いて。
フェリックスが大人しくソファで待っていると、ひげのおじさんが出てきた。その人がきっとオスカーと話していた人に違いないと思ったフェリックスは、ほとんどの部下の目線から外れたまま一人で入室した。ベルゲングリューンがドアを閉める前に入ったので、ロイエンタールもフェリックスが入ってきたことに気付かなかった。
ファーターと同じ服で、マントの色が違うオスカーを認め、フェリックスは安堵した。しかし、デスクに座り、書類に目を向ける表情は、フェリックスがこれまで見てきた父親の顔の、どれとも違い、少し驚いていた。自身が立てる小さな足音にも気付かないくらい集中しているその顔は、なんだか怖いくらいだった。
フェリックスがデスクについたとき、突然目の前が高く感じた。父親の顔がデスクに遮られて全く見えなくなってしまったのだ。
ロイエンタールは、ヘテロクロミアの視界の端に、もぞもぞ動くものが見え、驚いて顔を上げた。軍人として半生を過ごしてきた彼だったが、職場ではおよそ不釣合いなその「もの」に思わず笑っていた。
「フェリックスか?」
「う、うん」
フェリックスは両手を伸ばし、デスクに登ろうとしていた。その小さな手にロイエンタールが気付いたのだ。回り込む、という発想には至らなかったらしい息子の変わりに、ロイエンタールはすぐに立ち上がり、フェリックスの横に立った。やっと目と目を合わせることが出来たフェリックスは、慣れない広い空間で、ようやくホッとすることが出来た。
「ここまでどうやって来た? 部下もお前のことは言わなかったが」
「えとね、さっきまではファーターと一緒だったんだけど・・・」
「・・・そうか。それで、どこか見てきたのか?」
「ファーターのお部屋」
親友は、確かに忙しいだろうが、自分がフェリックスを案内すべきだと主張していたし、気を使ったのだろうと思ったロイエンタールは、フェリックスを抱き上げて、大本営を案内し始めた。
これまで、ファーターの家、オスカーの家、そして託児所くらいしか記憶にないフェリックスは、どこまでも続く廊下や、いくつもある部屋に圧倒されていた。建築中のルーベンブルンの方が大きいと聞いても、模型では想像もつかず、とにかく広いところでお仕事をしてるのだ、という風にフェリックスは理解した。
またフェリックスが最も嬉しそうに見ていたのは、戦艦の立体映像装置を見せたときだった。
「オスカーもせんかんに乗ったの?」
「ああ。これがトリスタンだ」
そして同時にファーターのベイオウルフを見つめながら、
「オスカーのと色違いで、マントの色と一緒だね?」
「そうだな」
その他の、駆逐艦や補給艦、救護艦まで見尽くし、フェリックスはため息をついた。
「これって、ほんとに飛ぶの?」
「・・・俺もファーターも、これで宇宙の端まで行ってたんだぞ」
子どもらしい疑問に、ロイエンタールは心の中で笑った。
今、この父子の前に誰かがいたら、そのクールな顔までもが微笑んでいたことを指摘したかもしれない。
最初、ロイエンタールがフェリックスの手を引いて廊下を歩いていたが、あまりにも歩調が合わず、そしてフェリックスの視線が低いので見学にもならないことに気付き、ロイエンタールは息子を抱き上げたまま歩いていたのだ。そして、すれ違う同僚たちが一様に目を見開き、壁に這うように驚いていたこと、そして見送った後姿を目をこすりながら凝視していたことを、ロイエンタールは知らなかった。一方360度首を回せるフェリックスは、自分たちがなぜそんなにも注目を受けるのかまではわからず、ただ首を傾げ、時々小さな笑顔を贈っていた。